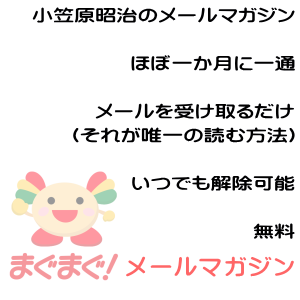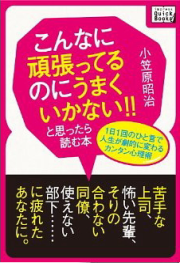1.どうして中小企業向けのコンサルタントなのか?
「わが社は、中小企業だから、中小企業専門のコンサルタントへ依頼しよう」
なんて、安易に考えちゃいませんか?
日本の企業の99.8%が中小
企業(90%が従業員数19人以下)ですから、わざわざ中小企業の名を冠するまでもありません。なのに何故、中小企業が専門なのでしょう?中小企業専門のコンサルタントを選ぶ前に、
どうして中小企業向けのコンサルタントなのか?
ちょっと考えてみましょう。「大企業向けの経営コンサルタントは、高額だから」という消去法で、中小企業の専門コンサルタントを選ぶと、面倒なことになる危険性があります。
なぜなら、中小企業専門の経営コンサルタントは、経営戦略すべてに影響を及ぼすからです。
- ユメ(経営ビジョン,事業拡大,多角化,アライアンス,事業承継,企業再生,創業)
- カネ(資金,資本,融資,株式,社債,税金,財務会計,コストダウン,事業継承,M&A)
- モノ(製造,在庫,物流,資材,設備,仕入れ,製品開発,各種規格,知的財産,ISO)
- ヒト(人事,採用,退職,解雇,制度,労務管理,従業員教育)
- キャク(事業開発,販路拡大,マーケティング,リサーチ,広告,広報,販促,営業,ブランド)
2.中小企業コンサルタントのメリット
中小企業専門の経営コンサルタントは、経営全般へ及ぶ、広い範囲のコンサルティングが得意です。メリットとしては、
中小企業の経営に関することならば、何でも相談できる
何でも関与できる、何でも知っているという汎用性。経営全般について相談できるのですから、その知識たるや、モノ凄いものがあります。
3.中小企業コンサルタントのデメリット
反対に、デメリットは何でしょう?何でもできるということを、翻せば、何にもできない
ということ。多岐にわたる
中小企業経営の中の、何のプロなのか、得意分野がない
ことです。たとえば、中小企業管理の専門資格を持った中小企業診断士は、
- 経営管理のプロであって、セールスのプロではありませんし、
- 税務や法務に至っては、税理士や弁護士の足元にも及びませんし、
- その弁護士や会計士にしたって、新商品を開発して市場導入できるか
というと、お門違いですし、そもそも、プロとして、
強みを発揮するのが難しい分野
に、通常は、進出しません。このように、プロのコンサルタントは、プロでいられる領域を知っています。
もし、中小企業の経営すべてに長けたコンサルタントがいたら、神様ではありませんか?
4.中小企業コンサルタントの危険性
つまり 「何でもできる = 何にもできない」中小企業コンサルタントが、経営全般にコミットして、影響を及ぼすわけですから、コンサルティング費用の高低を理由に、
「わが社は中小企業だから」
と、中小企業向け経営コンサルタントを選ぶと、結局は何も実にならず、
高いコンサルティングフィーを払うだけに終わってしまう
危険性があります。中小企業専門であっても、大企業専門であっても、コンサルタントへ依頼したことが裏目に出ることもあります。コンサルティング会社の皆様には怒られてしまうかも知れませんが、
コンサルタントは人によりけり
ですから、頼んだら危ない人も結構います。ご興味がありましたら、この本のamazonのレビューだけ御覧になっても、かなり参考になりますよ。

コンサルタントはこうして組織をぐちゃぐちゃにする。申し訳ない、御社をつぶしたのは私です
5.大手コンサルタント会社のメリットとデメリット
一方、大手のコンサルティング会社でしたら、各分野のコンサルタントを揃えていますので、どんな課題も対処できるでしょう。
しかし、複数メンバーのチームになりますから、それだけコンサルティング・フィーも高額に)
彼ら大企業向けの経営コンサルタントは、得意分野を持ち、その分野だけで、数年から数十年の経験があります。なぜなら、大企業の場合、もう既に経営コンサルタントが関与しているか、関与していたため、それ以上の実力がなければ通用しません(コンサルティング契約を受注できません)ので、
大企業向けのコンサルタントは、一人一人に得意分野があり、高度に研鑽
されています。ただし、クリティカルシンキング等の思考法を身につけた高学歴のコンサルタントの中には、黒いものを白だと言い張るための議論に学力を発揮する場合もあり、話が進まなくなることもありますので、要注意。
大手と中小の比較表
| 比較表 | 中小企業向けコンサルティング | 大企業向けコンサルティング |
| コンサルティング費用 | 低 | 高 |
| 営業拠点 | 本社のみ。あるいは国内数ヶ所 | 国内数十ヶ所から海外まで |
| 影響人数 | 1人~数百人 | 数千人~数万人 |
| コンサルティング先 | 経営者 | 担当社員 |
| コンサルティング内容 | 経営全般 | 専門分野 |
| コンサルティング内容 | 新規に導入 (新規、強化) | 既に導入済 (改良、深耕) |
| コンサルティング人数 | 経営者数名vsコンサルタント数名 | 担当チームvsコンサルティングチーム |
6.安さや無料を理由に中小企業の経営コンサルタントを選ぶ危険
コンサルタントは本来、「安定している企業が、もっと成長したくて依頼する専門家」ですから、高い、安いを気にする青色吐息の経営状態にある企業より、高額なコンサルタント料を支払える安定企業が、コンサルティング会社の売上を支えています。
そういう話をすると、「高額な出費のススメ」や「弱者は切り捨て」のように受け取られかねませんので、できるだけ伏せて分析していますが、「高いか?安いか?」で判断すると、
安かろう悪かろうの似非コンサルタントに当たってしまう危険性
が、大いにあることだけは、予め、ご承知おきの程を。実力に乏しい(たとえば、自分の強みや、ライバルとの違いさえ知らない)コンサルタントは、金額を安くしなければ、あるいは、値引きしなければ、依頼が来ないので、安くせざるを得ません。そんなコンサルタントに当たらないよう、関連記事の「コンサルタントの選びかた」も御覧になってみて下さい。
ここから先は余談です。
- 中小企業庁
- 中小企業基盤整備機構
- 中小企業情報化促進協会
- インターボイス
- 電通
- 売れる商品を作る力(商品力)か
- 売る力(営業力)
- どちらかがある
ことだけは確かです。
中小企業の経営には、売れるものを作る力か、売る力の、どちらかが必要
です。その二つが
- あるか?
- ないか?
を顧みるだけで、シンプルながらも分かりやすい自己分析になるはずです。
余談に余談を重ねますが、2009年の企業の99.7%(約432万)が中小企業でした。
それが、5年後の2014年には、385万事業者に減りました。わずか5年で、50万者が、消えて無くなったのです(法人は年間一万社減)
わかりやすく大雑把にいえば、一年間に10万人以上が、看板をおろして、再就職したり、無職になったり、最悪、首をくくっています。
決して、冗談ではありませんよ?
働き盛りの男性における自殺の原因は、すべての年代で首位を占める「健康問題」に並んで、倒産、事業不振、失業などの「経済/生活問題」が大きな割合を占めており、50代に至っては、「経済/生活問題」が、健康問題を凌駕して、一位になっています。
ぶっちゃけ、事業に失敗して首をくくる50代が多いということです。このように、中小企業が生き残るのは、どんなに大変か、お分かりになるでしょう。それゆえ、
中小企業を専門にするコンサルタントにも、その首をかけて、明確な理由を答えてもらいたい
ものですし、コンサルティングフィーが目的ではなく、自分の会社を育てるように、クライアントの中小企業を支援してもらいたいものですし、それを可能にする「独自の具体的なプラン」を提示してほしいと願うばかりです。