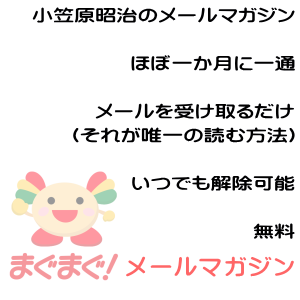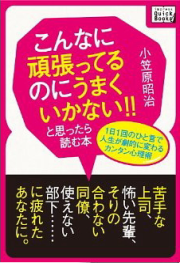地方の小さな町で開業するなら知っておきたいマーケティングと営業

お豆腐屋さんが、マーケティングに出会って変わりゆく様子を、楽し分り易く読めるよう、小説風に、創作してあります。
長い物語ですので、30分ほど、お時間がある時に、ごゆっくり、お楽しみ下さい。
(視覚的な区切りになって読みやすいよう、随所に、豆腐の写真が挿入されています)
また「シーン♯00/12」のナンバリングが、どこまで読み進んだか、しおりの代わりになるでしょう。
では、ここから始まります。
シーン#01/12『長野県飯島町の聖徳寺にて』
亡き父の後を継ぎ、小さな豆腐店の経営者になった加藤伊佐治が、叔母に会うのは、一年ぶりだった。
学生時代、東京で世話になった叔母には、アラフォーになった今でも、頭が上がらない。
「叔母さん、お久しぶりです」
「よっ!久しぶり」
「今日は、わざわざ、東京から、父の一周忌法要に来て下さって、ありがとうございました」

「ナニ言ってやがんだい。兄の法要に来るなんてぇのは、妹として、当然だろ?」
東京で、経営コンサルタントを営んでいる六条光代は、江戸っ子らしい伝法な口調で、
「で?豆腐屋の調子は、どうだい?」
と訊ねた。
伊佐治が視線を落として、
「調子は…」
と口ごもると、光代は、
「いけないよ」
と遮った。
「は?」
「暗くなるのが一番いけねぇ。笑いが絶えたら、笑売じゃないよ?」
「笑えませんよ、苦しいばっかりで」
「一体なにが苦しいって言うんだい?」
伊佐治は、思うように豆腐が売れなかった一年間を振り返った。すると光代は、
「あんた、豆腐を作って、豆腐を売ってんのかい?」
「そうです」

その答えを聞いて光代は「違う違う」とばかりにパーマ頭を左右に振り振り、
「誰に、売ってるんだい?」
「飯田町の人たちに、です」
「どうやって、売ってるんだい?」
「お店に買いに来る、お客さんに売っています。あと、飯田町のスーパーに卸してます」
「飲食店に卸すとか、やってないのかい?」
「飲食店に卸す?」
豆腐を、小売店へ卸すのではなく、飲食店へ卸す発想は、伊佐治にとって、初耳だった。
「叔母さん、その話、くわしく教えてください」

シーン#02 /12『加藤豆腐店へ向かう軽トラックの中で』
光代の話によると、商品を販売する場所は、三つあるという。それを、戦場と呼ぶ。
商品と、代金は、戦場で、交わされる。まさに、勝つか?負けるか?決する戦いの場で、
- お客さんのところへ行って売る攻城戦
- 店舗に籠もって売る籠城戦
- どこかへ商品を運搬して売る野外戦
の三つがある。これまでの伊佐治は、籠城戦一本やりだったが、光代に言わせれば、
「お客さんの城へ攻め入ったって、バチは当たらないんじゃないのかい?」
ということらしい。それが、飲食店への卸売りであった。
「それをチャネルっつーんだよ。マーケティングではナ」

「叔母さん、それ、やってみます。ありがとうございました」
「ちょいと待ちな」
「え?」
「売れると思って、スグに動いちまうと、主観の罠にハマるよ?」
「主観の罠?」
「あんたが、こいつぁ売れるぜ!と思ったって、買うほうが、買おうと思わなきゃ、売れやしねえだろ?」
「はあ」
「それを、とらぬ狸の皮算用ってんだ」

「狸…ねえ」
「主観で突っ走るから、売れなくて、落ち込むんだ。まずは、お客さんの話を訊かねぇことには、な」
「わかりました」
「で、いつまでに訊く?」
「いつまでにって言われても、毎日のルーティンワークがあるし、日曜は休みだし」
「ふっ。結局、訊かず終いってことになって、また、主観で突っ走んだろ?」
「はあ、まあ」
「だから売れねぇんだ。ふん」
「む!そこまで言われて黙ってちゃ、男が廃ります。わかりましたよ!1ヶ月以内に聞き取ります」
わざと怒らせて決意させる。還暦を越した光代らしい老獪な誘導だった。

シーン#03/12 『加藤豆腐店の一階工房にて』
「ところで、野外戦は、どうだい?」
「豆腐を、自転車の荷台に積んで、引き売りする時代は、もう終わりましたよ」
「あんた、豆腐を作ってんだろ?冷奴だけが、豆腐の食べ方じゃあンめえ」
「もちろん」
「だったら、豆腐ステーキ丼とか作って、軽トラに積んで、人が集まる場所で売ったらどうだい?」
「豆腐で、料理を作って売る?」

豆腐を作って売るのみならず、作った豆腐で、料理を作って売る。その発想も、これまで無かったが、豆腐職人の伊佐治には、今ひとつピンと来ない。
「僕の仕事は、豆腐を作ることであって、料理を作るのは、料理人の仕事です」
「ほっほう?日本国憲法に、そう書いてあるのかい?」
「け、憲法?」
「法は、人のためにあるんだ。じゃあ、豆腐は、誰のためにあると思う?」
「お客さんでしょう?」
「お客さんって、誰だい?」
「お店に買いに来る……」
「よーく思い出しな。誰が買っていくんだい?」
「主婦とか」
「でも、食べるのは、お子さんだったり、旦那さんだったりするわけだろ?」
「そりゃそうでしょう」
「じゃあ、主婦、旦那、子供の、誰に食べて欲しいんだい?」
「そんなの、決められませんよ」
「だったら、ファミリー向けの豆腐ってコトかい?」
「そういうことになりますね」
光代は、傍らにある豆腐容器のフィルムを手にとって、
「で?ファミリー向けの豆腐でございって、ドコに書いてあるんだい?」

フィルムには、どこにでもありがちな「絹」や「木綿」といった文字が、大書墨書されてあるのみだった。
「よしんば、書いてなくても、あんたが作る豆腐の、何がファミリーに向いているんだい?」
と問われて、伊佐治は絶句した。自分が作る豆腐の、何がファミリー向けなのか?
- 味なのか?
- 材料なのか?
- 形なのか?
- 成分なのか?
- 容量なのか?
- 食べかたなのか?
誰に食べさせたくて、どんな豆腐を作っているのか?考えたことも無かったからである。

シーン#04 /12『加藤豆腐店の一階工房にて』
「まだ分かんねえってぇんなら、ちィと、質問を変えようか」
と光代は、眼光鋭く光らせて、笑った。
「豆腐を買ったファミリーは、どうやって食べるんだい?」
「冷奴とか?味噌汁とか?麻婆豆腐とか?」
「語尾を上げるんじゃないよ、自信なさそうに」
「でも、どうやって食べているのか、想像するしか…」
「こンの、すっとこどっこい。あんたの作った豆腐が、どう食べられているのか、知らずに作ってんのかい」
「盲点でした」
「じゃあ、どうして『炒め料理専用の豆腐』を売らないんだい?」
「炒め料理専用の豆腐う?」
「炒め料理に、絹ごしを使えば、豆腐は崩れやすくなるし、木綿を使えば、絹の舌触りが失われるだろ?」
「でも、塩水で湯通ししたり、小さめに切ったりすれば、絹でも崩れませんが」
「そういうのを主婦は一番イヤがるんだ。面倒くせえのは、家事の大敵なんだよ」
「じゃあ、どうすれば?」
「新しい価値を作るのさ」

「新しい価値?」
「調理はカンタンなのに、とびきり美味しい豆腐炒め料理ができる豆腐なんてぇのは、どうだい?」
「そういえば、マーボーや、チャンプルーなどの、混ぜるソースや、炒め料理の素は売っているのに、専用の豆腐は、ありませんねえ」
「だろ?木綿の堅さでありながら、絹の舌触りを残した豆腐とか、さ」
「そんな豆腐、どうやって作るんですか?」
「いま、自分で言ったじゃねぇか。塩水で湯通しするって」
「あ」
「そういうことを研究するのが、メーカーの仕事だろ?」
「メーカー?」
「メーカーの意識が無いから、研究しないんじゃないのかい?」
「研究が仕事だと思ったことはありませんよ。僕の仕事は、豆腐づくり」
「そんなんじゃ、新しい豆腐なんざ出来っこねぇっつうの」

「新しい豆腐?」
「太子豆腐のような全国区の大手ライバルと同じ豆腐を作って、
- お客さんの人口は町民9,000人が最大で、
- 販路が無くて、
- 売れません~、
- どうしましょう~って、
ありきたりな敗者の弁だよ」
「あ痛たたた」
「全国規模の大手メーカーが出張ってきたら、こんなチッポケな豆腐屋なんざ、ひとたまりもありゃしない」
「ちっぽけは余計ですって」
「大手メーカーが出張ってくるまでの命ってこった。そうやって、木綿で首を絞めるかい?」
「それを言うなら、木綿じゃなくて、真綿でしょ」
「それとも、豆腐の角に頭をぶつけて死ぬかい?」

シーン#05 /12『加藤豆腐店の一階工房にて』
光代は、伊佐治の目を見据えて、真顔で言った。
「あんた、このままじゃ、左前だよ?十年後には倒産かも」
「脅かさないで下さいよ、叔母さん」
「脅かしちゃいないよ。だって、町民が減ってんだろ?」
「減っているみたいですね。実感は、ありませんケド」
「そうやって、ぬるま湯が、熱湯になって、ゆで蛙になっていくのさ」
「ゆで蛙の法則ですか。商工会のセミナーで聞きました」
「ゆで蛙なんざ、ウソっぱちだよ。熱くなりゃ、蛙だって逃げるわな」
「ウソっぱちって。たった今、叔母さんが、言ったばかりじゃありませんか」
「たとえだよ、たとえ。町民が減るってコトは、お客さんも減るってこった」
「そうですね」
「お客さんが減れば、売上も減る」
「そうですね」
「そうなりゃ、太子豆腐のような大手メーカーは、量産体制を布いてくるよ」
「どうして?ですか」
「少子高齢化で、日本国民が減ってんだから、売上を維持しようと、これまで以上に、あちこち地方の市町村へ卸してくるよ」

「確かに、大手のみならず、全体的に、豆腐の消費量は、減っています」
「ますます減るよ。買う人、つまり、人口が減ってんだから」
「作る人も減りました。豆腐関連の事業者数は、60年前から80%も減りました」
「安さで戦うからさ」
「豆腐は、安い食材だって、決まってますからね」
「価格で戦ってちゃあ勝ち目は無いね。慣習価格を決めるのは、大手メーカーだからね」
「全国に工場を持つ太子豆腐が価格を下げたら、我々零細は、従わざるを得ません」
「安くしなければ、売れなくなるからね」
「かといって、右ならえで安くすると、原材料費の大豆の高騰や、ボイラーの燃料費や、輸送費を差し引いて、利益が残りません」
「じわじわと、真綿で首を絞めるようなもんだ」
「そうですね。豆腐業界の半数以上が零細で、零細から先に、閉店していきますからね」
「あんたの零細豆腐屋も、閉店の憂き目に遭いたいかい?」
「零細は余計ですって」
「価格で大手と戦えないのなら、価値で戦うしかないだろ?」
「新しい価値…ですか」
「そ。あんたの選択肢は三つ。
- 売れる豆腐を作るか?
- 売れるように売るか?
- あれも出来ない、これも出来ないと、拒絶しながら、先細っていくか?
どれにするか?さ。ほれ、どれにする?」

シーン#06 /12『加藤豆腐店の一階工房にて』
「わかりました。父から引き継いだ店を潰すわけにはいきません。やります」
「何をやるんだい?」
「がんばって、新しい価値を作ります」
「がんばるのは、当たり前だってえの。みんな、がんばってんだよ」
「だから、新しい価値の作り方を教えてください」
「そんなモン、ありゃしないよ」
「え?無いんですか?」
「もしも、あったら、誰ひとり倒産しないっつうの」
「そりゃそうですが」
「あるって奴がいたら、お目にかかりたいね。そいつぁインチキかも知れないよ?あたしみたいなコンサルタントとか。がはははは」
「そうですか。無いんですか」
「ただ一つ、100%うまくいく保証は無いけど、マーケティングがある」
「マーケティング?」
「コンマ数%の可能性を探すのさ。それが、マーケティングの仕事」
「どんな可能性を探すんですか?」
「お客さんが、買う可能性を探すんだよ。お客さんが買うってことは、売れるってこった」
「単純な逆説ですね。お客さんが買う商品は、売れるし、反対に、売れる商品は、お客さんが買う商品」
「それを探して、創って、売れるように売るのがマーケティングさ」
「そのマーケティング、教えて下さい」
「あたしのマーケティングは、学校で教わるマーケティングじゃくて、現場で使うマーケティングだから、泥臭いよ?」
「そっちのほうが中小零細向きです」

「よし。じゃあ、マーケティングの軸は、お客さんだと思いな」
「軸は、お客さん」
「ところが、お客さんはシロウトだ。あんたはプロ」
「そうですね」
「プロだからこそ「こういう商品は如何ですか?」と提案できるってもんよ」
「なるほど。どんな新しい豆腐ならば、作れるのか、シロウトであるお客さんは、知りませんからね。プロの我々が考えなくちゃ」
「炒め専用の豆腐も、そうだろ?」
「そうですね。お客さんは、マーボやゴーヤチャンプル専用の豆腐なんて、気づきもしないけど、あったら、喜んでくれるかも知れません」
「ああ、そんな豆腐が欲しかったーって、お客さんが買えば、売れるだろ?」
「売れる商品は、お客さんが買う商品ですからね」
「でも、軸は顧客だから、お客さんに「マーボー専用の豆腐があったら買う?」って訊なくちゃ」
「それで、買うって人が多かったら、作ればいいんですよね」

「違うね。買うって人が多かったら…じゃなくて、買った人が多かったら、さ」
「え?買った人が多かったら?」
「それを、テスト・マーケティングっつうの」
「テスト・マーケティング?」
「お金を払うかも知れないという推測と、お金を払って買った事実は、ぜんぜん別物ってことを覚えておきな」
「買うと答えて、買わないかも知れないから、売れた事実を積み上げるんですね」
「それを、テストマーケティングの前に、徹底して、やるのが、あたしが独自に開発したR&S、リサーチ&セリングってえのさ」
「そのR&S、教えて下さい」
「じゃあ、買うかどうか、誰に訊く?」
「ファミリー向けの豆腐ですから、主婦…ですか」
「主婦?あんたが作る豆腐の…」
「何がファミリー向けなんだ?ってことですよね。うーん、こりゃ難題だなあ」
シーン#07 /12『加藤豆腐店の一階工房にて』
「いっそのこと、店名も、ファミリー豆腐店にしたら、どうだい?」
「ファミリーですか」
「あんた、大手メーカーと張り合って、ファミリー向けの作ってんだろ?」
伊佐治は、しばらく考え込んでいたが、
「言われて気づきました。僕が作りたいのは、ファミリー向けの豆腐じゃない」
「だったら、だれ向けなのさ?」
「そこがボンヤリしていて、まとまらないんですよね」
「いいかい?マーケティングは「誰」が第一だよ?なぜなら、価値観は、人によって異なるからね」
「大手メーカーの豆腐は、万人向けです。誰もが価値を認める豆腐ですよね」
「あんたが作る豆腐も、万人向けじゃ、販路も、技術も、生産拠点も、何もかも上回る、大手にゃあ勝てねえだろう?」
「おっしゃる通りです。そうして、80%の豆腐屋さんが消えてなくなりました」

「まったく、バレートの法則通りだね」
「パレート?」
「20対80の法則ってやつさ」
「ああ、ニッパチの法則」
「あんた、自分のことを知らずに、よく生き残ってこれたね」
「父が作った基盤の上に乗っているダケですよ」
「自分が何を売っているのか知らないんだから、お客さんだって、あんたから何を買えばいいか、分からないワな?」
「てっきり、豆腐を作って、豆腐を売っているんだと思っていました」
「それじゃあ、左前になって当たり前だわなあ?」
「豆腐を売っているようで、売っているのは、豆腐じゃなかったとは、ねえ」

「じゃあ、また、話を変えよう。あんた、結婚は?」
「藪から棒に、いきなりですか。残念ながら、まだですよ」
「もう、そろそろ、だろう?いい人は、いるのかい?」
「付き合っている人は、います。でも、今の豆腐店の経営状態じゃ、結婚なんて」
「結婚したかったら、繁盛させるこった」
「はい。繁盛させて、結婚します!」
「あんたと結婚したら、その人は、主婦になるわな?」
「そうですね」
「じゃあ、付き合っている女性の悩みは、何だい?」
「いろいろとあるでしょうケド、そうだなあ、ダイエットかな」
「太っているのかい?」
「僕から見れば、普通の体型ですが、本人は、気にしていて」
「女は皆、ダイエットに興味があるモンさ」
「叔母さんも?」
「あたしゃ女ご卒業。でも、女は、何歳になっても、べっぴんでいたいモンさ」
「そういうものですか」
「美容のためには、まず健康。美と健康はワンセットだからね」

「それです!」
「どれだい?」
「僕が作りたい豆腐は、女性の、美と健康のための豆腐です」
「わかりにくいね。もっと具体的には?」
「麻美さんのための豆腐です」
「麻美さんっていうのかい、あんたの好い人は」
「鈴木麻美といいます」
「ってえコトは、だよ?セグメントは女性。ダイエットに興味がある女性」
「セグメント?」
「たとえば、豆腐を二つに切れば、右と左、二つの豆腐になるだろ?」
「はい」
「右の豆腐が、一つのセグメント。左の豆腐も、一つのセグメント」
「ははあ。切り分けた塊のことですか」
「そう。マーケティングでは、性別や職業や居住地やライフスタイルで切る」
「なるほど。すると、僕が作りたかった豆腐は、
- セグメント1)女性=主婦のための豆腐。ひいては、ファミリー向けの豆腐
- セグメント2)独身女性のための豆腐
- セグメント3)ダイエットのための豆腐
- セグメント4)美容にいい豆腐
- セグメント5)健康にいい豆腐
ということになりますね。そうか。そういう構図だったのか」
「だんだん見えてきたようだね」
「セグメント(1)の女性向けだけで考えていたから、誰に売りたいのか、ハッキリしなかったんですね」
「これから、ターゲットは、麻美さんのような女性にするんだろ?」
「ターゲット?」
「セグメントという塊を、ターゲットにすることさ」

「見えました。僕の作りたい豆腐が!」
「どういう豆腐だい?」
「そもそも、豆腐は、美容と健康に良いダイエット食品なんです」
「どこが?」
「まず、大豆タンパクなので、腹持ちがいいんです。夕食にピッタリですね」
「違ぇねえ」
「カロリーが低くて、絹一丁150kcalですから、ごはん茶碗一杯以下です」
「ごはんの代わりに食べれば、低炭水化物ダイエットになるってぇわけだ」
「そうです。絹ごし豆腐を一丁も食べたら、男性でも、お腹一杯になります」
「そいで、栄養は?」
「絹ごしは、豆乳を絞らずに固めるので、水溶性のビタミンB1、B2、カリウムが豊富です」
「豊富だから、何だってんだい?」
「絹ごしは、疲れを取る栄養分が豊富ですから、仕事が終わったあとの夕食時に、冷奴で頂くのがオススメです」
「木綿は?」
「豆乳を絞って固めるので、水溶性のビタミンB1、B2、カリウムは流れ出ますが、ビタミンEは、絹ごしの2倍、カルシウムは、3倍も含まれています」
「カルシウムは、骨粗しょう症になりやすい女性にとって、嬉しい栄養素だね」
「崩れにくい木綿は、
- 温かい味噌汁、
- グラタン、
- 豆腐ステーキ、
- 照り焼き、
- 肉豆腐
などの、火を通す料理に向いています。肉や魚の代わりとしても」

「そういった豆腐の価値を、どうして商品パッケージに載せないんだい?」
「豆腐の価値?」
「うん、
- うまい、
- やすい、
- はやい、
- ダイエットに良い、
- 美容に良い、
- 健康に良い
ってこった」
「うまい、やすい、はやい…某牛丼チェーンと同じ価値があったとは、気づきませんでした」
「価値を知れば、売り方も変えられるってモンよ」
「どのように?」
「パッケージのフィルムに、絹とか木綿とか大書墨書するスペースがあったら、
- “腹持ちがよくて
- 低カロリーな
- ダイエットにいい
豆腐”って書きな。それだけで、新商品になっちゃうってえの」
「商品名を変えるだけで、新商品になるんですか?」
「あたぼうよ。ネーミングを変えたらヒットした商品なんざ、売るほどあらぁ」
「わかりました。次のパッケージフィルムを印刷するときは、絹や木綿の大文字をやめて、
- “低カロリーで
- 腹持ちがいい絹ごし”や
- “30秒でお腹いっぱいになる
- ダイエットにいい木綿”
にします」
「ほら、もう、新しい商品や、新しい価値が出来ただろう?」
「これまでの商品名を変えただけですもん。楽勝です」
質問に答えさせて、自ら気づかせ、やる気を出させる、光代のインタビュー・テクニックだった。

シーン#08 /12『加藤豆腐店の一階工房にて』
「それだけじゃないよ?ダイエットーフで商標を取りな」
「ダイエットーフ。うまいネーミングですね」
「あんたが儲かってから、ネーミング代 100万円 頂くことにするよ」
「ネーミングかあ。ダイエットーフのラインナップとして、充填豆腐ならば、
- “脂肪の燃焼を早める
- アミノ酸たっぷり豆腐”
という商品名を付けられるし、
- “血行の流れが良くなって
- お肌つやつや
- ビタミンEたっぷり豆腐”
という商品名も付けられます。ビタミンEなら、
- “肩こり
- 腰痛に
- ビタミンE
豆腐”なんてのも、商品名を変えるだけで出来上がりますね」
「血行や肩こり、腰痛なんてのは、薬事法があるから、よく調べてからにしな」
「はい。でも、誰に売りたいのか決まったら、アイデアが出てくるものですね」
「しばりのあるほうが、アイデアは、出やすいからね」
「なるほど。だから、誰に売る?って制約が重要なんですね」
「おうさ」
「わかってきました。お客さんは誰なのか?なんとなく、強力なライバルの大手メーカーと同じように、ボンヤリ考えていたのが、そもそも間違いでした」
「価格で勝負が決まっちゃ、勝てっこねぇだろ?」
「ですよね。値段以外、差別化になりませんものね」
「商品名を変えるだけの小手先じゃ済まないよ?本物の新商品を作らなきゃ」
「本物の新商品?これまでに無かった、新しい価値ですか」
「こんな豆腐、できるかどうか、あたしゃ知らないけど、美容と健康なら、
- お肌プルプル コラーゲンたっぷり豆腐とか
- お腹すっきり 食物繊維でできた豆腐とか
- お箸や お皿がなくても食べられる ひとくち豆腐(しょうゆ配合済み)とか
- 夜食に食べる 消化のよい 70kcalごま豆腐とか
美容や健康やダイエットに関連する豆腐さ」
「なるほど~。
- 枝豆を混ぜた枝豆豆腐や、
- 海草を混ぜたイギス豆腐、
- 青菜を混ぜた菜豆腐など、
変わり豆腐は沢山ありますが、機能食品としての豆腐は、見たことがありません」
「TPOによって、価値は変わるから、ごま豆腐にしたって、たったの70kcalに着目すれば、夜食として提案できるってモンよ」
「食べる時間を提案するんですね」
「勤め先で食べるという、場所を提案することもできるだろ?」
「それが、お箸がなくても食べられる、ひとくち豆腐ですね?」
「ウィダーイン豆腐ってぇのも、ある」
「飲むゼリーの豆腐版ですか」
「オケージョンで考えれば、結婚式で食べる紅白豆腐ってぇのもある」
「できるかどうか、研究してみます。あ、思わず、研究って言っちゃった」
「いいんだよ。メーカーで、マーケティングの花形といやあ、R&Dだからね」
「R&D?」
「リサーチ&デベロップメント。調査兼研究開発」
「リサーチ&デベロップメントかあ。新しい時代の豆腐屋っぽくて、いいですね」

シーン#09 /12『加藤豆腐店の一階工房にて』
「定番は抑えときな。この飯田町は、中央アルプスと南アルプス、二つのアルプスが見える町だから、“アルプスの 雪解け水で作った 豆腐シリーズ”略して「雪解け」もラインナップしときな」
「なるほど。ウチの豆腐を大きく分けると
- “雪解け”と
- “ダイエットーフ”
の二種類になるわけですね」
「そう。ダイエットーフは10案が出た。
- 低カロリーで 腹持ちがいい 絹ごし(商品名を変えるだけ)
- 腹持ちがよくて ダイエットにいい 木綿(商品名を変えるだけ)
- 脂肪の燃焼を早めるアミノ酸たっぷり豆腐
- 血行の流れが良くなって お肌つやつや ビタミンE豆腐
- 肩こり 腰痛に ビタミンEが効く豆腐
- お肌プルプル コラーゲンたっぷり豆腐
- お腹すっきり 食物繊維でできた豆腐
- お箸や お皿がなくても食べられる ひとくち豆腐(しょうゆ配合済み)
- おやつに 小腹が空いたら プリン豆腐 黒蜜豆腐 みたらし豆腐
- 夜食に食べる 消化のよい70kcalごま豆腐
だったね?これをアイデアフラッシュという」
「これまで、絹と木綿の2種類だった豆腐が、10種類に増えました。あとは、僕の技術で、作ることが出来るかどうか、研究するだけです」
「他にも、骨そしょう症の対策に、カルシウム豆腐とか、ナンボでも出てくるだろ?」
「はい。機能で考えたり、TPOで考えたり、切り口次第だってことがわかりました」

「雪解けシリーズは、それらの豆腐とは違うよ?生活に密着した豆腐さ」
「生活に密着?」
「あたしみたいに連れ合いを亡くした高齢者や、独身女性向けに、お一人さま豆腐が、まず一つ目」
「なるほど。女性の一人暮らしに、豆腐一丁は、食べきれないかも知れません」
「お一人さま豆腐は、容器を小さくするだけ」
「お子さま向けヨーグルトのようなイメージですか」
「そうさね」
「容器を小さくすれば、値段も安くなりますね。これは売れるかも」
「まあ、待ちな。まずは、リサーチするネタを作ってからの話さ」
「リサーチ&セリングですね」

シーン#10/12 『加藤豆腐店の一階工房にて』
「ところで、どの家庭でも作る豆腐料理は、なんだい?」
「豆腐の味噌汁です」
「だったら、味噌汁の具に、
- “切れてる 絹ごし”
- “切れてる 木綿”
なんてぇのは、どうだい?」
「切れてる豆腐ですか。ナベに入れるだけですから、手間が省けますね。アウトドアに、いいかも」
「卸す先は、スーパーじゃないよ?」
「もちろん!家族向きには、売れないでしょう」
「そう。それをチャネルというのさ」
「卸す先を間違えると、売れるものが、売れなくなるんですね?」
「切れている豆腐なんか、主婦向けに売ったって、売れっこなかろうよ」
「誰に向けて売るのか?マーケティングで最も重要なのは“誰”でしたね」
「うん。
- 絹、
- 木綿、
- それぞれを一人前用、
- 二人前用、
- 三人前用
と容器を変えて分けるだけで、6種類になるだろ?」
「さらに、大きめ切りと、小さめ切りに分ければ、12種類になりますね」
「そうやってアイテムアップを増やしていくのさ」
「ははあ。
- 雪解けシリーズがラインナップ。その中の、
- 切れてるシリーズがアイテムアップ
になるわけですね」
「飲み込みが早いね。さすが、あたしの甥っ子だ」
「さっきまで、馬鹿あつかいしていたくせに」
「フッ。
- ゆきどけシリーズと、
- ダイエットーフシリーズ、
二つを合わせて、カトウ豆腐ブランドになるのさ」
「ブランドなんて、考えたこともありませんでしたよ」
「そうやって、商品体系を増やしていくのさ」
「なにやら、マーケティングっぽくて楽しみです」

「他に、人気メニューは?」
「やっぱり、冷奴でしょう」
「だったら、冷奴専用の豆腐ってぇのは、どうだえ?」
「え?そんな、何種類もの冷奴を作る製法や、素材なんか、ありませんよ」
「豆腐を提案するんじゃなくて、食べ方を提案すんのさ」
「豆腐レシピでしょ?それは、料理研究家の仕事じゃありませんか」
「べらぼうめ。そうやって、豆腐職人の殻に閉じこもるから、いけねぇんじゃねえか」
「そうでした。僕は、もう、職人じゃない。R&D、マーケターなんですよね?」
「そう。小さな店の職人だと思えば、それ以上の発展は望めねえ。これからはR&Dだと思って、マーケティングを勉強しな」
「でも、どうやって提案するんです?レシピのシールでも貼ります?」
「そんな余分なコストかけるこたぁねえ」
「そうか!パッケージのフィルムに印刷するだけでいいんだ」
「そうさ。一年12ヶ月ごと、月替わりで、12の冷奴レシピを載せて提案しな」
「それなら、材料や製法を変えなくても、冷奴専用の豆腐が出来上がります」
「たとえば、だよ?
- 揚げ玉を乗せた たぬき冷奴
- すりニンニクとオリーブオイルと塩をかける イタリアン冷奴
- きざみ海苔とゴマ油と塩でいただく 韓国風冷奴
いくらでも出て来んだろ?」
「そりゃもう!インターネットで検索すれば、何百と出てきます」

シーン#11/12『加藤豆腐店の二階六畳間にて』
「インターネットといえば、売り方だ」
「はい」
「ここまで、誰に売るか?何を売るか?は決まった。あとは、どうやって売るか?」
「飲食店へ卸売りですか?」
「人口9,000人の町の飲食店じゃ、食材をスーパーで仕入れる店が、ほとんどだろうよ」
「そうですね。あと、飲食店のほうから買いに来ます」
「飲食店経営っつったって、一町民だからね」
「飲食店ルートは、望み薄かも」
「需要を作り出すにしても、市場が小さ過ぎらぁ。あきらめるしか、あんめぇ」
「叔母さん。マーケティングは、可能性を探す仕事なんでしょ?」
「あたりきしゃりきよ」
「だったら、あきらめる前に、訊くだけ訊いたって、いいじゃありませんか」
「おっと、こいつぁ一本とられたね」
「何を訊けばいいんです?」
「くれぐれも「豆腐いりませんか?」なんて聞くんじゃないよ?」
「はい」
「お店の看板メニューになる豆腐を作りますから、話を聞かせてくださいって持ちかけな」
「わかりました。ダメ元で、やるだけやってみます。町の飲食店の活性化にもなるし」

「インターネットに話を戻すけど、ホームページは出しているのかい?」
「はい。僕の手作りですが」
「見せてみな」
二人は、加藤家の居住スペースがある、二階の居間へ階段を上った。
光代が、仏壇に手を合わせている間に、伊佐治はパソコンを立ち上げて、
「これです」
と声をかけた。パソコンを覗き込んだ光代が思わず、
「なんだい?こりゃ。今日びの高校生でも、もっとマシなモンを作るよ」
と叫んだほど安っぽいデザインのトップページに、通販商品が並んでいる。他のページは、
- 会社概要が1ページ、
- 問い合せが1ページ、
- お店の地図と外観の写真が1ページ
合計4ページのサイトだった。
「あんた、このホームページから、注文が入るってぇのかい?」
「いいえ」
「そうだろうよ。これじゃ、無いほうがマシだよ」
「そんなにヒドイですか?」
「ナメきってるとしか思えないね。当面は、顔本(フェイスブック)を使いな」
「わかりました。やってみます」
「あと、メールマガジンを発行しな」
「メルマガですか」
「それと、料理サイトのクックパッド。豆腐料理だけを投稿するんだよ?」
「豆腐屋さんの豆腐料理というわけですね」

「そいつらで、プロモーションしてみな」
「プロモーション?」
「今日、これまで、豆腐の価値について、話してきただろ?」
「はい」
「それを書いて、インスタで、
- 豆腐や料理の写真、
- 製造工程や
- 日本アルプスの動画
を添えて、サイトへ転載してみな」
「読者数は、増えますか?」
「増えないよ」
「え~?それじゃ意味ありませんケド」
「読者数が問題なんじゃない、何かを発行することで、コンテンツを作るしばりを自分に課すのさ」
「〆切りですね?」

「そう。しばりが無くちゃ、書かねぇもんさ」
「書くネタが、続きそうにありませんケド?」
「ダイエットと、美容と、健康について勉強すりゃ、ナンボでも書けんだろ?」
「豆腐屋のサイトですから、豆腐について書くのがスジだと思うんですが」
「そんなスジ、煮込みにして喰っちまいな」
「は?」
「あんたが作る、豆腐の価値について、思い出してみぃつうの」
「あ、そうでした。僕が作る豆腐は、女性の美と健康のための豆腐でした」
「それが価値なんだから、女性の美と、健康と、ダイエットと、豆腐について書くのさ」
「僕に書けますか?」
「いきなり100点なんか無理だって。書いていくうちに、だんだん上手くなっていくモンさ」
「そういうものですかね」
「何事も、練習、練習。練習なしで、上手くなろうなんて、甘ぇのよ」
「そうですね」
「あんたは、豆腐のプロなんだから、あとは、ダイエットと、美容と、健康について勉強していきゃ、回り回って、豆腐づくりのネタにもなるってぇの」
「やってみます。いえ、やり遂げます」

「いつまでに作る?」
「アレもコレも、忙しくなってきたからなあ」
「この、たわけ者が。左前なクセして、今まで忙しくなかったのが不思議なくらいだよ」
「面目ありません。じゃあ、一ヵ月後までに」
「よし。出来たら教えとくれ」
「わかりました」
「電車の時間がきたから、あたしゃ帰るけど、もし何か分からないことがあったら、いつでも電話しな」
「ありがとうございます。叔母さんのお陰です」
「いいってことよ」
「身内じゃなかったら、僕、話せなかったと思います」
「ん?」
「僕たち、経営者の仲間は、中小零細企業ばっかりですが、みんな、具体的に、どうすればいいか、真剣に、悩んでいます」
「だろうね」

「でも、具体的な何かが示されると、
- うちには合わないとか、
- それは違うとか、
つい、拒否してしまいます」
「珍しいこっちゃないよ。ほどんどの地方企業は、みんな、そうさ。専門的には、バイアスかかってんの」
「僕も、そうでした。保守的というか」
「職人気質だからね。商圏は決まりきっているし。地縁血縁で、がんじがらめだし」
「その点、僕はラッキーでした。叔母さんの言うことなら、信じられますので」
「あたしと同業のコンサルタントには気をつけな。ピンキリだから」
「はい。今日明日から、何かが急に変わるわけありませんケド…」
「そりゃそうさ」
「僕は、どこへ向かおうとしているのか、ハッキリしましたし、何をすべきか、具体的に分かりました」
「それを、戦略っつうんだよ」
「たくさんの作戦を、ひとつずつ、実行していきます。ありがとうございました」
「うん。死んだ兄の分まで、頑張んな」
そうして光代は、帰っていった。
まるで、光代という名の台風が過ぎ去った後のように、伊佐治の気持ちは、晴々としていた。

シーン#12/12『その後の加藤豆腐店』
叔母が帰ってからというもの、僕の忙しさは、言語に絶した。
休日返上は当たり前。
今にして思えば、よくも堂々と「日曜は休み」なんて、叔母に言えたものだ。穴があったら入りたい。
- 朝は、豆腐の仕込み。
- 昼は、配達やリサーチ&セリング。
- 夜は、サイト作り
それに加え、時間の合間を見つけては、ダイエットと、美容と健康の本を読んで、勉強、新商品の開発と、まさしく、寝る間も惜しんで動き回った。
麻美さんも、仕事が休みの日には、手伝いに来てくれた。僕は、
「無給で働いてもらうのは、申し訳ないから」
と断ったが、
「いずれは豆腐屋の女房になるんだから、今のうちに勉強しておかなくちゃ」
と、快く手伝ってくれた。

女性の視点でアドバイスしてくれたのも助かった。
高校の同級生だった主婦たちが、豆腐ステーキを作るのに苦労しているという他愛のない茶飲み話も、麻美さんから聞いた。

豆腐ステーキが、人気メニューであることは、飲食店へのリサーチ結果と一致していた。
かたちを崩さずに豆腐ステーキを焼くのは、プロでも、意外に難しいという。
それらの情報をもとに、豆腐ステーキ用の豆腐作りに取り組んでみた。
誰かが望んでいる料理や、誰かが困っている料理に、新しい価値が、あるかも知れない。
- 僕の仕事は豆腐づくり
- 料理は料理人の仕事
と分けて思い込んでいた自分がウソのように、新しい発想が湧き出てきた。これが、マーケティングを身に付けた効果なのか。

調べてみると、豆腐ステーキ用の豆腐は、すでに市販されていた。
取り寄せて食べてみると、確かに、豆腐ステーキ用の豆腐かも知れない。
しかし、僕が作りたい豆腐ステーキ用の豆腐は、豆腐じゃなくて、美と健康に良いステーキだった。
そこで、生しぼりという豆腐の原型から作ることで、歯ごたえがあって、焼きやすくて、美味しい、ステーキ専用の豆腐が完成した。
「お肉の形にしましょうよ。メイン料理になるから」
という麻美さんの意見を取り入れ、厚さ3センチのステーキ肉状にして、肉に似た網目の焼き色を付けた。
「ステーキソースも付けたほうが喜ばれると思う」
「そうだね。
- 和風と
- 洋風、
二つのソースに分けるだけで、二種類の商品になる」
いつの間にか、R&Dで考える癖が身についていた僕だった。
このステーキ専用豆腐を、長野県全域にスーパーを展開しているツルヤへ持っていったところ、試しに一週間だけ、置いてもらえることになった。
それがきっかけとなり、
- テレビ信州、
- 信越放送、
- 南信州新聞、
- 長野朝日放送、
- 長野エフエム、
- 市民タイムス、
- 須坂新聞、
- 伊那毎日、
- 信濃毎日新聞、
- 軽井沢新聞、
- 飯田エフエム、
- あづみ野エフエム、
- エフエム佐久平
等に取り上げられ、電話が鳴り続く大反響を得、少量といえど、生産が間に合わない、嬉しい悲鳴が今も続いている。

豆腐ステーキ専用の豆腐は、インターネットからも引き合いが来た。
なんと、海外の大手スーパーが、豆腐ステーキ用の豆腐を取り扱いたいという。
しかし、豆腐は、鮮度が命だけに、この話は、現在ペンディング中だが、
「マーケティングは、効果が絶大」
と確信した。
価値を売れば、商品も売れる。日本中へ売れる。世界中へ売れる。
町の人口が一万以下まで減ったからと、もう、市場縮小に不安がることはない。

それにしても驚いたのは、豆腐の知識の曖昧さであった。
間違いないかどうか調べながら書いていくうちに、職人としての自分の知識が曖昧だったことに気づいた。
伝える、と、教えるは、同義であり、教えるのは、教わるよりも、難しかった。
職人というプライドの上に、あぐらをかいて、教えることを放棄してきた結果、いざ伝えようとしても、伝えられなかった。
こうして、改めて、豆腐の勉強を始めることになった。
おかげで、ずいぶん、豆腐の知識が豊富になった。
叔母さんが
「書いていくうちに、だんだん、上手くなっていく」
と言っていたのは、このことだったのか…と驚いた。

加藤豆腐店という店名も変えることにした。
社名には、意味が込められるからだ。
女性の美と、健康を売っているのだし、海外進出も視野に入り始めたので、
びけん(美容と健康の美健とうふ店)
という店名に変えた。
美健ブランドのタグラインも作った。
Biken Bean Curd for Beauty & Healthcare
このネーミングは、無形文化遺産に登録された和食へ貢献できる店名だと自分では気に入っている。
わずか一日、2~3時間で、マーケティングの要点のみ凝縮して教えてくれた叔母の顔が脳裏に浮かんだ。
「豆腐ステーキ丼とか作って、軽トラに積んで、人が集まる場所で、売ったらどうだい?」
この最初の叔母の一言に、豆腐ステーキという、答えが隠されていたのである。
そういえば、叔母も女性だった。忘れていた。

すると、以心伝心だろうか、「朝の仕込みが早いので」と一緒に暮らし始めた麻美さんが、
「叔母さんから、電話よ」
と、受話器を持って来てくれた。
「もしもし?伊佐治です」
「もしもしって言うんじゃないよ。コッチじゃスケベな意味になるんだから」
「コッチって?一体どこにいるんですか?」
「ドイツだよ。ドイツじゃ、豆腐が、どエライ人気だよ?」
「ドイツですってぇ?」
「ああ、和食ブームで、ヘルシーな豆腐を、肉の代わりに、食べ始めたのさ」
「肉の代わりに?」

「あんたのステーキ豆腐、コッチで、爆発的に売れるかも知れないよ」
「ドイツに、ステーキ豆腐を作る豆腐屋さんは、無いでしょうからね」
「ああ。そんじゃ、あばよ」
そう言い放って、せっかちな叔母は、電話を切った。
「ドイツかあ」
こみあげてくる可笑しさをこらえながら、僕は、振り返って、
「ねえ、麻美さん。新婚旅行、ドイツへ行こうか?」

【おしまい】
この物語はフィクションです。実在する人物や団体名とは関係ありません。