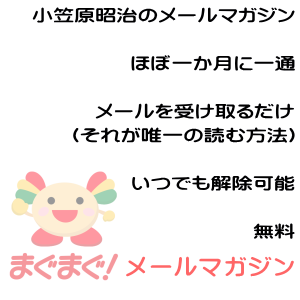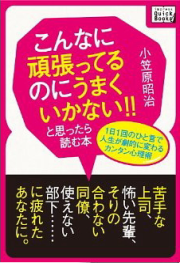金の切れ目が縁の切れ目になる経営戦略
資金(お金)は数値化できますので、経営者は、社内へも、
「売上目標○○円を達成せよ」
「コストを○○%削減せよ」
と、数字を求めます。
個人が暮らしていくのに、毎月、
「これだけは要る」
という最低限の生活資金があるように、経営にも、毎月、必要最低限の運営資金が必要です(わかりやすくいえば、社員へ給料を払わなければなりません)から、経営者が数字を求めるのは、無理からぬことです。
その、必要最低限の基準値を、ノルマと呼ぶ企業もあれば、売上目標と呼ぶ企業もあります。
それら、売上目標や、ノルマを回転軸に、会社は動きます。企業は、ボランティアではなく、営利追及団体ですから、当たり前な話です。
そうして、社員は、命じられたままに「売り上げ目標を達成しよう」と、売上目当てに商品を売り歩きます。
すると、悪質商法に現れがちな弊害として、しつこかろうと、嫌われようと、顧客の迷惑なんざ知ったこっちゃありません、売ったモン勝ち。
売れたら顔を出さなくなるのも、当然。売上金(お金)さえ入れば、目的達成ですから、お金を払ったお客さんは、用済みになります。
そうして、成果主義、能力主義、実力主義、利益至上主義、売上至上主義等が誕生してきました。
それはそれで、その企業の経営方針ですから、誰から文句を言われる筋合いのものではありませんが、お金を欲しがる経営者が悪いのではありません。
もちろん、社員が悪いわけでもありません。
良し悪しの問題ではなく、資金が底をつけば倒産という現実問題あるのみ。
経営者にとって、失格の烙印であり、従業員や取引先にとって、最悪の結果です。
それ(倒産)だけは、避けなければなりません。
こうして、ほとんどの企業が、利益の数字を目標に企業活動しています。
企業が利益の数字を追う理由は、会社を潰さずに維持するため
カネ(資金)さえあれば、売上高や、利益が、たとえゼロでも、会社は存続できます。
なにも難しい話じゃありません、あなた個人が貯金するのと同じことで、貯金さえあれば、収入がなくても、暮らしていけるでしょう?
逆に、売上や利益があっても、資金が無ければ、たちまち倒産してしまいます。
来月の給料を、売掛金や手形に喩えてみると、分かりやすいかも知れません。
来月も、定額の給料が振り込まれる予定だからといって、手持ちの現金を使い果たしてしまったら、おにぎり一つ買えなくなりますね?
だから、お金を計画的に使いますし、それは、個人も法人も同じこと。
お金の使い道を決めるのが、個人であれば、あなた自身ですし、法人であれば、経営者です。
このように、経営は、資金が第一ですから、決算書の数字が、何よりも第一ですし、銀行から融資を受けるにしても、決算書の数字がものを言いますし、経営相談の相手は、税理士が最多です。
「社長、税理士の先生が、お見えになりました」
「専務、銀行の融資係から、お電話です」
「常務、顧客A社の手形が、不渡りになったようです」
と、毎日のように繰り返していると、おのずから経営者の頭の中は、数字まみれになります。
なので、経営者が「売上を増やせ」と檄を飛ばすのは、私腹を肥やしたいというよりも(もちろん、最終的には、経済的に豊かになりたいからにしても)、会社を潰すことなく、ますます成長させるべく、資金を減らさず、増やすために他なりません。
資金を増やすために
「商品を売れ」
と号令をかけ、号令一下のもと、売るのが役目の営業部は動きます。なので、
経営者「売上を増やせ」
↓
営業部長「商品を売ってこい」
↓
営業社員「買って下さい」
と、資金を増やす目的の経営戦略が、商品を売る営業戦略へ垂直落下するのは無理からぬこと。
しかも、できるだけ早く売りたい。早ければ早いほど売上も早く入ってきますからね。
商品を売って、売上を増やしたいのですから、一年先なんて話は鬼が笑います。
先月も、「いま売れ!すぐ売れ!もっと売れ!」
今月も、「いま売れ!すぐ売れ!もっと売れ!」
来月も、「いま売れ!すぐ売れ!もっと売れ!」
こうして、ほとんどの企業が、資金を回収する経営戦略に直結した営業戦略を
布いています。
経営者にとって、最も重要なのは資金ですから、人件費であれ、仕入れであれ、水光費であれ、社会保険料であれ、税金であれ、毎月きちんと、資金(お金)が出て行くため、資金を回収しようと、営業力や商品力の強化を図ります。
お客様よりも、お金さま優先になる経営戦略の理由
商品を売って、売上を伸ばすのは、当たり前なように思いますよね?
その当たり前な常識に、思わぬ落とし穴が潜んでいます。
「売り上げ目標を達成しろ!」
と檄を飛ばせば、営業部員の意識は、売上金という数字へ向かい、商品を売るのが目的になります。
そうなると、代金と引き換える商品を大事にします。
お客様は、商品が欲しいのではなく、商品で得られる便益(メリット)を欲しがっているにもかかわらず、パンフレットを広げて、商品の説明から始めます。
営業戦略は、お金と商品を交換する商取引が戦略目標になり、量と回数と単価と期日が目標値になります。
もちろん、企業は営利追及団体ですから、お金と商品を交換するのは当然です
が、では、会社の商品を、誰のお金と交換するのでしょう?
いわずもがな、お客さんですよね?
代金を払ってくれるのはお客さんですし、商品を買ってくれるのも、お客さんですから、商売は、売上金よりも、商品よりも、お客さんが最優先であることはサルにもわかります。
サルでも分かる話なのに、売上目標を追いかけると、お客さんよりも、売上金ほしさに、商品を売り込みます。
お客さんが買いたい「価値」よりも、ナンボ売れたか?に価値を見出すようになります。
それに、売上を稼ぐのも、商品を売るのも、会社の都合であって、お客さんの都合ではありませんね?
ところが、売る側の立場に立つと、お客さんの立場に立つよりも先に、商品を売って、売上金を稼ごうとします。
いつの間にか、全社を挙げて、お客さまよりも、お金さま第一主義になります。
売上を増やすには、商品を売るより先に、顧客を増やす経営戦略
企業は、営利追及団体ですので、商品を売るのが当然です。
売上がなければ、企業活動し続けられませんから、利益を追うのも当たり前です。
ライバルを含めた殆どの企業が、そうであるように、みんな、お金ほしさに商売しています。
お金を得て、払って、会社を維持し、生活を維持し、願わくば、さらに発展し、より多くの収入を得て、経済的に満足するために企業活動します。
なので、
「売上目標を達成しろ。売上金の数字を増やせ」
という命令が下ります。すると、社員は、お金を増やすために動きます。
商品を売ろうとすると、売れてナンボですから、もう、顧客の都合よりも、自社の都合を優先し、商品の販売が大命題になります。
そうなると、営業マンは、商品の説明から始めます。
請われているなら、説明しなければなりませんが、請われなくても説明するとしたら、そりゃ押し売りです。
これこの通り、商品を売って、売上を増やそうとすると、お客さんは、二の次、三の次。お金が第一、商品が第二、自社の都合が第三で、顧客そっちのけになります。
はて、お客さんは、あなたの会社の都合で、商品を買うのでしょうか?
お客さんは、自分の都合で、価値(メリット)を買うんですよね?
商品が優先しますと、お客さんが求めている価値よりも、商品そのものに価値が生じます。
お金が第一になると、代金と交換する商品が第二になり、自社や、業界の都合が第三になります。
あまつさえ、カネのためなら何でもやるブラック企業も現れます。
お金が目的ですから、取引が終われば、お客さんとの縁も切れます。給料が少なければ会社を辞める従業員も現れます。
みんな、カネのために集まり、カネのために散ります。これすなわち、カネの切れ目が、縁の切れ目になる経営。
それを良しとする経営者や企業もあるでしょう。拝金主義者や、売上優先主義者ならば、それでも構いませんが。
ところが、お客さんは、お金を払いたくて、買うわけではなく、その商品によって得られる価値が欲しくて買います。
価値は、人によって異なりますから、価値を理解してくれる人=顧客が企業にとって第一です。
第一義は、売上でも、商品でも、自社の都合でもありません。顧客にとっての価値です。
売上(お金)よりも先に、顧客を増やす(社会に受け入れられる)ことが、企業活動の目的ですから、
「新しいお客さんを紹介してくれるかも知れない擬似客を○○人増やせ」
と、人脈の人数を増やし、
「既存顧客の流出を阻止せよ」
と、顧客数を維持して、その中から優良顧客を増やすのが正解ではありませんか?
ということは、売り上げを増やしたければ、
「売上を増やせ」
という命令ではなく、商品を売るより先に、
「優良顧客を増やす」
ことが最優先。優良顧客が、売上の70~80%を支えてくれるからです。次に、
「お客さん全体の数を増やす」
売上の数字よりも、顧客の数字です。そのために、ゆくゆくは顧客になるかもしれない、
「味方を増やす」
金額の数字を追う経営ではなく、人脈の数字を追う経営です。
経営者と社員の目的は、会社と生活、維持の二文字で一致する
経営する第一の目的は、会社の維持(倒産させないこと)です。
一方で、従業員が働く目的は、給料です。
給料を、衣食住の生活費や、買いもの等へ支払います。
つまり、給料を得る第一の目的は、生活の維持(路頭に迷わないこと)です。
経営者と従業員の、お互いの目的は、支払い、つまり、維持で一致します。
給料を支払う側と、受け取る側の、対立構造ですと、労使は対決しますが、人も、企業数も減っている今、これからの時代は、減りゆく顧客の奪い合いになりますので、労使ともに力を合わせ、会社を、生活を、維持していかなければなりません。もう、労使が対決している時代ではなくなりました。
お互いに力を合わせ、現状を維持するには、従業員も、経営(ヒト・モノ・カネ)の仕組みを知って、経営者の意識を持ち、お客様を奪われないように防御すること。
守るだけでは、攻められてしまいます。ライバルたちも、生き残るのに必死ですから、攻勢を強めてきます。
攻撃は最大の防御なり。経済的に豊かになるには、お客様を増やし、できれば発展させること。
経営意識とは?社員とアルバイトの違い
なぜ、財務戦略は、経営者の考える作戦で、社員の考える作戦ではないのでしょう?
一億円を、銀行から借りるのが、一般的な社員の役割ではないからです。
毎月、一定額が振り込まれる給料とは異なり、売上金は、一定ではありませんから、足りない時もあります。
そんな時、銀行からお金を借りる責任者は、会社の代表者である経営者です。
借りた資金を返せなくて、首をくくるのも、社員ではなく、経営者です。
なので、財務戦略は、従業員の考える作戦ではなく、経営者が考える作戦です。
その作戦に、従業員が、建設的な意見を具申するのは結構なことですが、異を唱えるのは越権行為ですから、たとえば、
「給料が安い。増やしてくれ」
と、経営者の財務戦略を否定し、昇給を要求するのであれば、
1 昇給のための資金を自力で銀行から借りてきて会社へ融通するか(投資家や株主として経営に加わるか)
2 転職するか(転職する自由が、従業員には、あります)
3 ご自分の職掌の範囲で、利益を高め、給料が増えて当然にするか?
いずれか?です。
三つ目が、経営者でなくても、経営意識を持つということです。
それ(企業価値の向上)に協力するのが、社員(法人の一員)ですし、協力する必要など無いのが、生活費のために働くパートやアルバイト(非正規)です。
ボクサーや役者になるといった夢を叶えるまでの生活費のために働いているアルバイト、および、貯金や生活費を増やそうと働くパートは、自分の為に働く自由がある代りに、保険や年金といった雇用コスト(福利厚生という第二の給与)が発生しませんし、雇用契約の解除も可能です。
一方の社員には、給料の他に、いろいろな雇用リスクが伴いますし、労働基準法で厚く守られています(解雇四要件により解雇できません。一方の経営者は株主が解雇できます)から、社員と経営者の役割は同じであるわけがなく、もしも、社員でありながら、会社の維持や成長に協力したくなければ、アルバイトやパートとして雇用契約し直せばいいだけの話です。
ちなみに、派遣社員も、実質はパートやアルバイトと同じです。社員という言葉のマジックに惑わされぬよう。
人を育てるのが経営者で、プロを育てるのがリーダー
三大経営資源であるヒト・モノ・カネのうちの、カネです。
資金さえあれば、売上や利益が無くても経営し続けられますから、売上よりも、
利益よりも、資金が第一で、資金が第一だからこそ、社外の銀行や、株主が、経営に参画してきます。
しかし、借りる(出資してもらう)だけで経営は成り立ちませんし、貸す(出資する)側にしても、利子(配当)という利益が目的ですから、
「これくらい儲けるつもり」
と見込んだ利益を稼ぎ出し、配分しなければなりません(営業外収益は別です)
借りられる企業は幸いです。いざというとき、融資してもらえますから、経営危機を乗り越えられます。
その時のために、借りる必要がなくても借りて、利子を払い続け、信用を得ておき、経営が悪化した時に、借りられるよう備えている企業も多々あります。
リーマンショックのように、いつ、どこで、どんな災難が降りかかってくるかわかりませんからね。
しかし、借りる当てがなければ(借りる当てがあっても)、商品を売って利益を稼ぎ出さなければなりません。商取引が企業活動ですから。
商品、つまり、ヒト・モノ・カネのうちの、モノですね。
メーカーなら、製品のみならず、資材や倉庫や工場の設備もモノに入りますし、非メーカーなら、社屋や、車両や、十万円以上の什器備品までモノに入ります。
カネとモノがあっても、ヒトがいなければ、企業活動できませんから、たとえ社長一人であっても、ヒトが必要不可欠です。
人が必要不可欠とはいえ、誰でも良いわけではありません。どこの企業も優秀な人材が欲しい。
しかし、自己投資に惜しみない優秀な人材は、待遇の良い大企業へ就職してしまいます。
その土地に就職したいから等の理由なくして、安月給では、優秀な人材を確保できるはずがありません。
そうなると、育てる他ありません。
育てるには、世に様々なセミナーや研修は溢れていますが、経営者のポリシーと、企業のポリシーを示し、信頼の拠りどころを見せてあげましょう。
行動理念の実例をもとにした物語
理念とは考え方のことです(辞書を引いてみて下さい)
経営理念は、経営者の考え方ですから、経営者の言葉になります。
一方、企業理念は、法人としての考え方ですから、経営理念をもとに会社全体で(企業体として)作ります。
十代の常識と、五十代の意識は、親子ほどに違いますので、
「これくらい、わかるだろう」
という思い込みに囚われずに、理解できるかどうか、守れるかどうか、すべての年代の従業員に聞きながら作るとよいでしょう。
目に見えない法人の人格を言葉にして、キャラ立ちさせると、社の個性が際立ち、ライバルとの差別化になり、社会や、まだ取引の無い新規客に信用してもらえて、既存客からの信用も増し、顧客を増やせます。
企業の理念の中には、
・行動の理念
・価値観の理念
・理念の可視化
があります。その中から、行動の理念について、物語を一つ挙げましょう。
まるで初心者が運転しているようにトロトロ走るスポーツカーの後ろを、運送会社のトラックが走っていました。
スポーツカーのハンドルを握っているのは、女性でした。トラックの運転手は、若い男性ドライバーでした。
トラック運転手は、
「女の運転はヘタだな。それに、若いクセして、こんな高級車に乗りやがって」
と、つい、イラッとして、クラクションを鳴らし、幅よせ(いやがらせ)して、抜き去っていきました。
後日……
運送会社の社長あてに、暴力団の組長から、電話が入りました。
スポーツカーの女性ドライバーは、組長の妻でした。トラックの車体に書かれてある運送会社名を覚えていて、夫(組長)へ話したようです。
社長は、すぐさま、すべての予定をキャンセルし、組事務所へ謝りに行き、たっぷりと、人の道を聞かされて帰ってきました。
帰社するやいなや、顧客満足に価値を置いて経営している社長は、(筆者へ相談して)行動理念を作り、社内へ発表しました。
行動基準…他車優先・歩行者最優先
行動指針…模範ドライバーたれ
行動規範…歩行者や、他の車に、迷惑をかけるな。
歩行者がいる横断歩道では停車。
むやみにクラクションを鳴らすな。
幅寄せするな。
ダッシュボードに足を乗せるな。
運転席で寝るな。
弁当を食べるな。
タバコを吸うな。
お客様は、どこかで見ている。
それ以来、この運送会社は、地元警察から表彰される優秀なドライバーの集団になりました。
理念は、危機管理にも、社の名誉にもなる実例です。