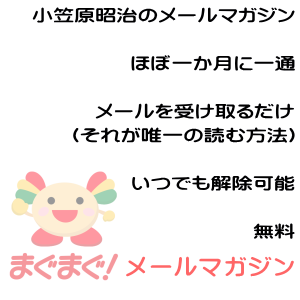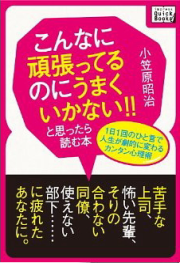金の切れ目が縁の切れ目になる経営戦略
資金(お金)は数値化できますので、経営者は、社内へも、
「売上目標○○円を達成せよ」
「コストを○○%削減せよ」
と、数字を求めます。
個人が暮らしていくのに、毎月
「これだけは要る」
という最低限の生活資金があるように、経営にも、毎月、必要最低限の運営資金が必要です(わかりやすくいえば、社員へ給料を払わなければなりません)から、経営者が数字を求めるのは、無理からぬことです。
その、必要最低限の基準値を、ノルマと呼ぶ企業もあれば、売上目標と呼ぶ企業もあります。
それら、売上目標や、ノルマを回転軸に、会社は動きます。企業は、ボランティアではなく、営利追及団体ですから、当たり前な話です。
そうして、社員は、命じられたままに「売り上げ目標を達成しよう」と、売上目当てに商品を売り歩きます。
すると、悪質商法に現れがちな弊害として、しつこかろうと、嫌われようと、顧客の迷惑なんざ知ったこっちゃありません、売ったモン勝ち。
売れたら顔を出さなくなるのも、当然。売上金(お金)さえ入れば、目的達成ですから、お金を払ったお客さんは、用済みになります。
そうして、成果主義、能力主義、実力主義、利益至上主義、売上至上主義等が誕生してきました。
それはそれで、その企業の経営方針ですから、誰から文句を言われる筋合いのものではありませんが、お金を欲しがる経営者が悪いのではありません。
もちろん、社員が悪いわけでもありません。
良し悪しの問題ではなく、資金が底をつけば倒産という現実問題あるのみ。
経営者にとって、失格の烙印であり、従業員や取引先にとって、最悪の結果です。
それ(倒産)だけは、避けなければなりません。
こうして、ほとんどの企業が、利益の数字を目標に企業活動しています。
企業が利益の数字を追う理由は、会社を潰さずに維持するため
カネ(資金)さえあれば、売上高や、利益が、たとえゼロでも、会社は存続できます。
なにも難しい話じゃありません、あなた個人が貯金するのと同じことで、貯金さえあれば、収入がなくても、暮らしていけるでしょう?
逆に、売上や利益があっても、資金が無ければ、たちまち倒産してしまいます。
来月の給料を、売掛金や手形に喩えてみると、分かりやすいかも知れません。
来月も、定額の給料が振り込まれる予定だからといって、手持ちの現金を使い果たしてしまったら、おにぎり一つ買えなくなりますね?
だから、お金を計画的に使いますし、それは、個人も法人も同じこと。
お金の使い道を決めるのが、個人であれば、あなた自身ですし、法人であれば、経営者です。
このように、経営は、資金が第一ですから、決算書の数字が、何よりも第一ですし、銀行から融資を受けるにしても、決算書の数字がものを言いますし、経営相談の相手は、税理士が最多です。
「社長、税理士の先生が、お見えになりました」
「専務、銀行の融資係から、お電話です」
「常務、顧客A社の手形が、不渡りになったようです」
と、毎日のように繰り返していると、おのずから経営者の頭の中は、数字まみれになります。
なので、経営者が「売上を増やせ」と檄を飛ばすのは、私腹を肥やしたいというよりも(もちろん、最終的には、経済的に豊かになりたいからにしても)、会社を潰すことなく、ますます成長させるべく、資金を減らさず、増やすために他なりません。
資金を増やすために
「商品を売れ」
と号令をかけ、号令一下のもと、売るのが役目の営業部は動きます。なので、
経営者「売上を増やせ」
↓
営業部長「商品を売ってこい」
↓
営業社員「買って下さい」
と、資金を増やす目的の経営戦略が、商品を売る営業戦略へ垂直落下するのは無理からぬこと。
しかも、できるだけ早く売りたい。早ければ早いほど売上も早く入ってきますからね。
商品を売って、売上を増やしたいのですから、一年先なんて話は鬼が笑います。
先月も、「いま売れ!すぐ売れ!もと売れ!」
今月も、「いま売れ!すぐ売れ!もっと売れ!」
来月も、「いま売れ!すぐ売れ!もっと売れ!」
こうして、ほとんどの企業が、資金を回収する経営戦略に直結した営業戦略を布いています。
経営者にとって、最も重要なのは資金ですから、人件費であれ、仕入れであれ、水光費であれ、社会保険料であれ、税金であれ、毎月きちんと、資金(お金)が出て行くため、資金を回収しようと、営業力や商品力の強化を図ります。
お客様よりも、お金さま優先になる経営戦略の理由
商品を売って、売上を伸ばすのは、当たり前なように思いますよね?
その当たり前な常識に、思わぬ落とし穴が潜んでいます。
「売り上げ目標を達成しろ!」
と檄を飛ばせば、営業部員の意識は、売上金という数字へ向かい、商品を売るのが目的になります。
そうなると、代金と引き換える商品を大事にします。
お客様は、商品が欲しいのではなく、商品で得られる便益(メリット)を欲しがっているにもかかわらず、パンフレットを広げて、商品の説明から始めます。
営業戦略は、お金と商品を交換する商取引が戦略目標になり、量と回数と単価と期日が目標値になります。
もちろん、企業は営利追及団体ですから、お金と商品を交換するのは当然です
が、では、会社の商品を、誰のお金と交換するのでしょう?
いわずもがな、お客さんですよね?
代金を払ってくれるのはお客さんですし、商品を買ってくれるのも、お客さんですから、商売は、売上金よりも、商品よりも、お客さんが最優先であることはサルにもわかります。
サルでも分かる話なのに、売上目標を追いかけると、お客さんよりも、売上金ほしさに、商品を売り込みます。
お客さんが買いたい「価値」よりも、ナンボ売れたか?に価値を見出すようになります。
それに、売上を稼ぐのも、商品を売るのも、会社の都合であって、お客さんの都合ではありませんね?
ところが、売る側の立場に立つと、お客さんの立場に立つよりも先に、商品を売って、売上金を稼ごうとします。
いつの間にか、全社を挙げて、お客さまよりも、お金さま第一主義になります。
売上を増やすには、商品を売るより先に、顧客を増やす経営戦略(サンプル)
企業は、営利追及団体ですので、商品を売るのが当然です。
売上がなければ、企業活動し続けられませんから、利益を追うのも当たり前です。
ライバルを含めた殆どの企業が、そうであるように、みんな、お金ほしさに商売しています。
お金を得て、払って、会社を維持し、生活を維持し、願わくば、さらに発展し、より多くの収入を得て、経済的に満足するために企業活動します。
なので、
「売上目標を達成しろ。売上金の数字を増やせ」
という命令が下ります。すると、社員は、お金を増やすために動きます。
商品を売ろうとすると、売れてナンボですから、もう、顧客の都合よりも、自社の都合を優先し、商品の販売が大命題になります。
そうなると、営業マンは、商品の説明から始めます。
請われているなら、説明しなければなりませんが、請われなくても説明するとしたら、そりゃ押し売りです。
これこの通り、商品を売って、売上を増やそうとすると、お客さんは、二の次、三の次。お金が第一、商品が第二、自社の都合が第三で、顧客そっちのけになります。
はて、お客さんは、あなたの会社の都合で、商品を買うのでしょうか?
お客さんは、自分の都合で、価値(メリット)を買うんですよね?
商品が優先しますと、お客さんが求めている価値よりも、商品そのものに価値が生じます。
お金が第一になると、代金と交換する商品が第二になり、自社や、業界の都合が第三になります。
あまつさえ、カネのためなら何でもやるブラック企業も現れます。
お金が目的ですから、取引が終われば、お客さんとの縁も切れます。給料が少なければ会社を辞める従業員も現れます。
みんな、カネのために集まり、カネのために散ります。これすなわち、カネの切れ目が、縁の切れ目になる経営。
それを良しとする経営者や企業もあるでしょう。拝金主義者や、売上優先主義者ならば、それでも構いませんが。
ところが、お客さんは、お金を払いたくて、買うわけではなく、その商品によって得られる価値が欲しくて買います。
価値は、人によって異なりますから、価値を理解してくれる人=顧客が企業にとって第一です。
第一義は、売上でも、商品でも、自社の都合でもありません。顧客にとっての価値です。
売上(お金)よりも先に、顧客を増やす(社会に受け入れられる)ことが、企業活動の目的ですから、
「新しいお客さんを紹介してくれるかも知れない擬似客を○○人増やせ」
と、人脈の人数を増やし、
「既存顧客の流出を阻止せよ」
と、顧客数を維持して、その中から優良顧客を増やすのが正解ではありませんか?
ということは、売り上げを増やしたければ、
「売上を増やせ」
という命令ではなく、商品を売るより先に、
「優良顧客を増やす」
ことが最優先。優良顧客が、売上の70~80%を支えてくれるからです。次に、
「お客さん全体の数を増やす」
売上の数字よりも、顧客の数字です。そのために、ゆくゆくは顧客になるかもしれない、
「味方を増やす」
金額の数字を追う経営ではなく、人脈の数字を追う経営です。
経営戦略とは?ヒト、モノ、カネを動かして、会社を維持する、経営者の作戦(サンプル)
経営戦略
と聞いただけで、もう、
「難しそう」
と思ってしまいませんか?それもそのはず、経営戦略の定義は百花斉放で、唱える人によって異なり、
- 組織の中長期的な方針や計画を指す用語という解釈もあれば、
- 経営の基本目標を実現する事業活動の指標という解釈もあれば、
- 経営理念を具現化するための具体的な方法論という解釈もあれば、
差別化、集中化、5F、SWOT、コストダウン等々、経営戦略の定義や解釈は百人百様です。
経営戦略を布く法人が百人百様であるため、おそらく「どれが正しい」という定義は無く(経営学では、あるかも知れませんが)、
「当社の経営戦略はドミナント戦略」
も正しければ、
「当社の経営戦略はM&A」
も正しいのです。その経営戦略で売り上げ、利益を出しているのですから。
しかし、それでは、経営戦略は企業ごとに異なり、定義は存在しないということになりますので、わかりやすく、短く、経営戦略を定義しますと、経営戦略とは、
「ヒト、モノ、カネを動かして、会社を維持する、経営者の作戦」
です。
なぜ、経営者の作戦なのかというと、社員(ヒト)を増やせば、給料(カネ)を払わなければなりませんし、社員(ヒト)が増えれば、モノも増やさざるを得ません。
たとえば、営業活動でアポイントを取るには、電話器と席(モノ)が必要ですし、納品するには、運搬用の車両が必要なように、働く環境(モノ)を整える必要がありますし、モノを整えるには先立つ資金(カネ)が必要ですから、資金を借りるか、稼ぐ他ありません。
このように、経営資源のヒト・モノ・カネは三連鎖しています。
切り離せるものではないヒト・モノ・カネを動かして、どうやって利益(売上)を稼ぎ出すか?という経営者の作戦が、経営戦略であり、ヒト・モノ・カネを連鎖させて考え、最適に配分するのが経営者の役目です。
経営者と社員の目的は、会社と生活、維持の二文字で一致する
経営する第一の目的は、会社の維持(倒産させないこと)です。
一方で、従業員が働く目的は、給料です。
給料を、衣食住の生活費や、買いもの等へ支払います。
つまり、給を得る第一の目的は、生活の維持(路頭に迷わないこと)です。
経営者と従業員の、お互いの目的は、支払い、つまり、維持で一致します。
給料を支払う側と、受け取る側の、対立構造ですと、労使は対決しますが、人も、企業数も減っている今、これからの時代は、減りゆく顧客の奪い合いになりますので、労使ともに力を合わせ、会社を、生活を、維持していかなければなりません。もう、労使が対決している時代ではなくなりました。
お互いに力を合わせ、現状を維持するには、従業員も、経営(ヒト・モノ・カネ)の仕組みを知って、経営者の意識を持ち、お客様を奪われないように防御すること。
守るだけでは、攻められてしまいます。ライバルたちも、生き残るのに必死ですから、攻勢を強めてきます。
攻撃は最大の防御なり。経済的に豊かになるには、お客様を増やし、できれば発展させること。
人を育てるのが経営者で、プロを育てるのがリーダー
三大経営資源であるヒト・モノ・カネのうちの、カネです。
資金さえあれば、売上や利益が無くても経営し続けられますから、売上よりも、
利益よりも、資金が第一で、資金が第一だからこそ、社外の銀行や、株主が、経営に参画してきます。
しかし、借りる(出資してもらう)だけで経営は成り立ちませんし、貸す(出資する)側にしても、利子(配当)という利益が目的ですから、
「これくらい儲けるつもり」
と見込んだ利益を稼ぎ出し、配分しなければなりません(営業外収益は別です)
借りられる業は幸いです。いざというとき、融資してもらえますから、経営危機を乗り越えられます。
その時のために、借りる必要がなくても借りて、利子を払い続け、信用を得ておき、経営が悪化した時に、借りられるよう備えている企業も多々あります。
リーマンショックのように、いつ、どこで、どんな災難が降りかかってくるかわかりませんからね。
しかし、借りる当てがなければ(借りる当てがあっても)、商品を売って利益を稼ぎ出さなければなりません。商取引が企業活動ですから。
商品、つまり、ヒト・モノ・カネのうちの、モノですね。
メーカーなら、製品のみならず、資材や倉庫や工場の設備もモノに入りますし、非メーカーなら、社屋や、車両や、十万円以上の什器備品までモノに入ります。
カネとモノがあっても、ヒトがいなければ、企業活動できませんから、たとえ社長一人であっても、ヒトが必要不可欠です。
人が必要不可欠とはいえ、誰でも良いわけではありません。どこの企業も優秀な人材が欲しい。
しかし、自己投資に惜しみない優秀な人材は、待遇の良い大企業へ就職してしまいます。
その土地に就職したいから等の理由なくして、安月給では、優秀な人材を確保できるはずがありません。
そうなると、育てる他ありません。
育てるには、世に様々なセミナーや研修は溢れていますが、経営者のポリシーと、企業のポリシーを示し、信頼の拠りどころを見せてあげましょう。
社是とは?社是の作り方
社是(しゃぜ)と、社訓(しゃくん)は、社○と社○で、文字づらが似ているため、内容も同じように勘違いしがちですが、異なります。
社是は、国是のように、「この考え方や、方向性で行く」 という(企業の)大方針を、一つだけ、数文字に凝縮したセンテンス(まとまった内容を表現して、言い切ったフレーズ)のこと。
たとえば、国是と比較してみましょう。
江戸時代の日本は「鎖国」(二文字)が国是でした。
今の本は「非核三原則」(五文字)が国是です。
スイスの「永世中立」(四文字)も国是といっていいでしょう。スイスは国是と明言していませんが。
そうした数文字が、
「あなたの会社では、何になりますか?」
というのが社是です。
国是が、国家に一つなように、社是も、一社に一つです。
「いやいや。何ヶ条も、長々と書き連ねた社是だって、あるだろう」
って?
はい、あります。
それが、社是社訓、経営理念の違いを混同させる原因になっていますので、先ず、言葉の意味から復習してみましょう。
社是とは、辞書によると
「会社や結社の経営上の方針・主張。また、それを表す言葉」
だそうです。要するに、経営の方針ですね。
「それじゃ、経営方針と一緒じゃないか」
って?
その通りです。言葉の意味を追究すれば、そうなります。そこで、一社に一つという社是の単一性が活きてきます。
社是は一つ、経営方針は複数可ですから、経営方針の中から最も重要で普遍的な条項を一つ抜き出して社是に掲げれば、社是の出来上がり。
では、方針の意味とは?というと、同じく辞書では、
「めざす方向。物事や計画を実行する上の、およその方向」
だそうです。
東西南北、どこへ行くか?方向性ですね。つまり、辞書によると、社是とは、
「あっちへ進む」
という経営の方針と方向性を指します。
両者に共通しているのは、「どこへ行くか」ざっくりとした方角です。
方角ですから、抽象的で構いません。たとえるなら、飛行機で行くとか、船で行くとか、幾らで行くとか、何月何日の宿泊先はドコにするといった具体性は、あとの話で、先ずは、行き先の方面ありき。
東西南北どこへ行くか?それが、国家の場合、
鎖国=[是]幕府だけが貿易して儲けるぞ。[非]基督教を禁止するぞ。
非核三原則=[是]米国の核の傘に入るぞ。[非]戦争しないぞ。
永世中立=[是]自分の国は自分で守るぞ。[非]軍事同盟しないぞ。
という是非になり、これが、企業の場合、社是になります。なので、経営方針を一つの是非にまとめるだけで、社是の出来上がり。
では、理念は?というと、同じく辞書では、
「ある物事についての、こうあるべきだという根本の考え」
で(考えで)、社是である方向性も方針も、理念(どうして、その方向へ進むのか?その針路へ進む考え)に含まれます。
社是も「考え」、社訓も「考え」、理念も「考え」ですので、社訓も、経営理念も、一緒(=考え)となって判断に迷うわけです。
理念が、考え(ポリシー)ということは、経営方針も、経営戦略も、経営指針も、経営哲学も、経営思想も、企業理念も、企業戦略も、企業憲章も、企業綱領も、企業信条も、企業使命も、行動指針も、行動規範も、すべて理念(ポリシー)に含まれます。
すべて理念(ポリシー)に含まれるから、経営理念と、社是の区別が、つきにくい
のです。実際、そう考えている(一緒でいいと考えている)企業は多いようで、
社是と、経営哲学が、同じ意味だったり、
社是が、社訓だったり、
企業憲章という名の、経営理念だったり、
偉人の遺した人生訓が、そのまま社是になっていたり、
漢字数文字で表した「修身」のような道徳だったりします。
だから、社是社訓と経営理念がゴチャ混ぜになり、何ヶ条も、長々と書き連ねた社是だって、あるし、漢字一文字や、二文字の社是だって、あるワケですが、それで社是を作ることができるのなら、それでいいのです。
あればいいのです。無ければ、伝わりませんので。
どんな社是を作るかは、その企業の自由であって、正誤の問題ではなく、
経営理念 〉 社是
の位置関係であるに過ぎません。
しかし、
「それじゃ抽象的すぎて、社是を作れないよ」
という企業のために、筆者なりの定義をまとめてみますと、社是は、一社に一つ、この方向で行くという大方針を数文字に凝縮したセンテンス(まとまった内容を表現して言い切ったフレーズ)です。
以上の三項目が、社是には、揃っていること。
そう定義すると、ほとんどの企業の社是が、社是ではなく、経営理念や、経営方針や、社訓になってしまいますが(本当)、よそ様はよそ様として、
「経営者の考えという広義ではなく、社是の意味に焦点をあて、こだわり抜いて、狭義に考えたい」
という企業の皆様は、一社に一つ、この針路だけは守り抜くという大方針を、数文字に凝縮したセンテンス(まとまった内容を表現して言い切ったフレーズ)で社是を作ってみてください。
3つの条件という制限がありますから、漠然とした「作りなさい」よりも考えやすいはずです。むしろ、
造語ならオリジナルの独自性
が出ます。たとえば、キューピー社の社是が、造語です。
造語ですから、世界に一つ、他に、同じ社是は、存在しません。
ちなみに、社訓も、「親を大切にしなさい」という、平易な、他社には見られない珍しい社訓で、中学生にもわかりやすく、社員には親がいて、社員である前に、人間であるという本質を突いた見事な社訓です(が、筆者、キューピー社の回し者でも、ファンでもありません、事実を述べたダケでした)
社訓とは?社訓の作り方
社訓は、従業員に守ってもらいたい訓示や訓戒のこと。
家訓と同じです。訓の前に「社」がつくか「家」がつくかの違いです。
家訓のほうがピンと来やすい方々もおられましょう。
江戸時代の商家は、今の会社に相当しますから、たとえば、三井家の家訓(家憲)を借りますと、
一、同族の範囲を拡大してはいけない。同族を無制限に拡大すると必ず騒乱が起こる。同族の範囲は本家・連家と限定する。
一、結婚、負債、債務の保証等については必ず同族の協議を経て行わねばならぬ。
一、毎年の収入の一定額を積立金とし、その残りを同族各家に定率に応じて配分する。
一、人は終生働かねばならぬ。理由なくして隠居し、安逸を貪ってはならぬ。
は見切りが大切であって、一時の損失はあっても他日の大損失を招くよりは、ましである。
一、他人を率いる者は業務に精通しなければならぬ。そのためには同族の子弟は丁稚小僧の仕事から見習わせて、習熟するように教育しなければならぬ。
一、大名貸しをしてはならぬ。その回収は困難で、腐れ縁を結んでだんだん深くなると沈没する破目に陥る。やむを得ぬ場合は小額を貸すべし、回収は期待しない方がよい。
以上のように、あなたの会社の従業員に、これだけは守ってもらいたい創業者や経営者の訓示(訓えや戒め)を社訓といいます。
作るのは、創業者や、経営者ですから、社訓には、経営者の思想や哲学が反映されます。経営思想や経営哲学あっての社訓です。なので、
経営思想や経営哲学を箇条書き
にして下さい。
その中から、
「社員のみんな、こうしてくれ。これだけは守ってくれ」
という願いを抜き出してください。それが社訓になります。
英語では、社訓も、社是も、クレド(company credoまたはcompany creed)なので、近ごろでは、英語(やラテン語)で、クレドと呼び、社訓と社是を同一解釈する企業が増えてきました。
それはそれで、その企業の自由とはいえ、しかし、
「英訳すると、同じ意味なんだから、社訓と社是は一緒」
という解釈では、あまりにも日本語が可哀想ですよね(笑)