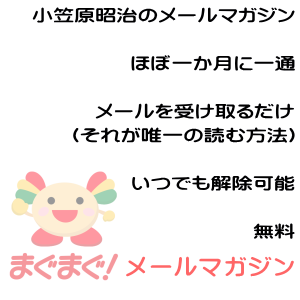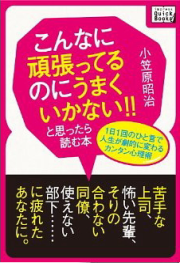S科学的に行われるマーケティングは、データベースを使うなど、科学的であるがゆえに、重大な3つの欠陥がある。
一つ目が、数字で判断すること
わかりやすい例が年齢で、30代と定義すれば、29歳も、41歳も、埒外になるが、現実には、流行語大賞にもなったアラフォーのように、数字で割り切るのが難しいグレーゾーンがある。それ(29歳や41歳)を取りこぼしてしまう。
クォリフィケーションにもナーチャリングにも数字が必要で、予め定めた数字に基づき、上記のように、見込み客に○×をつける定量調査の落とし穴である。
二つ目は、売る側が、売るために立てる作戦であること
マーケティングは、売る側の立場で進められる。
ひどい例になると「絶対に売れる!」と確信して準備してきたにもかかわらず、蓋を開けてみたら、まったく売れずに赤字撤退ということが、よくある。
特に中小零細企業の皆様は注意して頂きたい他社事例の研究として、大手企業のマーケティングには、水面からでは見えづらい、水面下の活動が多分にある。
たとえば、ある日用品メーカーは、顧客のインサイトを探るべく、一般家庭に、一週間ほど泊まり込むことさえある(エスノグラフィ調査)
そうした予算と労力と時間をかけた調査結果が、商品へ反映される。
大手企業とは、中小企業は、生産設備や人員といった有形資産も異なれば、知名度やソフトウェア、特許といった無形資産も異なる。
三つ目は、顧客とは何か?商売の基本が疎かになりがちな傾向にあること
マーケティングを突き詰めると顧客へ行き着き、顧客を突き詰めると顧客満足へ行き着くが、一つ目と二つ目の理由に関連し、マーケティングは、売る側の独善性によって顧客満足を阻害する危険を孕んでいる。
マーケティングが行き着くところの「顧客」とは何か?特に見込み客を含め、顧客は、
- データや計算で割り切れる存在 = 数字でもなければ、
- お金を払う権限をもつ強い存在 = 神様でもなければ、
- 下手に出なければならない存在 = ご主人さまでもなければ、
- 商売を抜きにして付き合う存在 = 友人でもなく、
- 精神的に一人では生きていけない弱い存在 = 人間
である。そう考えれば、顧客の謎が解ける。